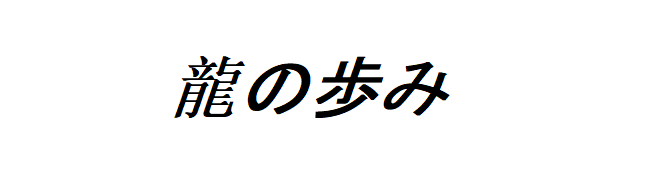南唐はなぜ契丹に屈しなかったのか?「偽りの唐」が契丹を震え上がらせた?
南唐は、志気こそあれど運に恵まれず、実力もまた十分でなかった悲劇的な国家であった。その建国は「簒奪」によるもので、正統性には欠けていたが、大節においては汚点なく、遼(契丹)と天下を争う気概を持ち、中国統一の野望を抱いていた。その運命は、後に自らを滅ぼすことになる北宋と酷似しており、まさに「北宋の前身」とも言える。
南唐は、志気こそあれど運に恵まれず、実力もまた十分でなかった悲劇的な国家であった。その建国は「簒奪」によるもので、正統性には欠けていたが、大節においては汚点なく、遼(契丹)と天下を争う気概を持ち、中国統一の野望を抱いていた。その運命は、後に自らを滅ぼすことになる北宋と酷似しており、まさに「北宋の前身」とも言える。
あまり知られていないが、南唐はかつて「皇漢的」とも呼ぶべき大胆な行動を取ったことがある。遼の太宗・耶律徳光が中原に侵入し、後晋を滅ぼした際、南方の漢人諸国はこぞって契丹に臣従した。たとえば、現代の「皇越(こうえつ)」支持者たちが最も称賛する呉越国も、このとき契丹に朝貢し、その支配を認めたのである。
『遼史・太宗本紀』:「冬十月辛丑、有司奏す、燕・薊大熟す。癸卯、呉越王、使を遣わして来貢す。」
しかし、契丹は南方で唯一、南唐という「釘」にぶつかった。後晋滅亡の混乱に乗じて、呉越が胡人に屈服した一方、南唐の君臣は北伐を主張し、江南の偏安を打破して中原の民を契丹から解放しようとした。南唐は後晋の将軍や官僚の帰順を積極的に受け入れ、契丹との覇権争いを公然と宣言したのである。
『資治通鑑・後漢紀』:
「晋密州刺史皇甫暉、棣州刺史王建、皆契丹を避け、衆を率いて唐に奔る。淮北の賊帥、多く唐に命を請う。
唐虞部員外郎韓熙載、上疏して曰く:『陛下、祖業を恢復せんとす。今まさにその時なり。若し虜主北帰して、中原に主あらば、則ち図り難し。』」
ところが、南唐はその時、福建での戦い(閩国併合直後)に主力を拘束されており、北伐の機を逸してしまう。
『資治通鑑・後漢紀』:「時、方や福州に兵を連ね、北顧する暇なし。唐人皆これを恨み、唐主も亦これを悔ゆ。」
だが、劣勢の中でも南唐は一歩踏み出した。元宗・李璟は使者を遣わし、遼の太宗・耶律徳光に対し、驚くべき要求を突きつけた——「南唐の工匠を長安に派遣し、唐の帝陵を修復させてほしい」と。
南唐は自らを唐太宗の子・呉王李恪の末裔と称していた(ただし、実際には徐姓の出自であり、偽称と見るのが通説である)。この要求は、形式上、南唐が李唐の正統継承者であることを契丹に認めさせようとする、外交的挑戦だった。
もし遼がこれを承諾すれば、南唐が中原の正統支配者であることを事実上認めるに等しかった。耶律徳光は当然、これを拒絶した。
『契丹国志』:「唐主、使を遣わして帝の晋滅を賀し、且つ長安に詣でて諸陵を修復せんことを請う。帝、これに従わず。」
しかしこの南唐の行動は無意味ではなかった。契丹は南方の南唐の動向に神経を尖らせ、北方の太原節度使・劉知遠への警戒を緩めた。その隙を突いて劉知遠は挙兵し、契丹を背後から攻撃。開封を奪還し、後漢を建国して漢人の国を再興したのである。
このように、五代十国という混沌の時代において、「偽りの大唐」が一時的にも契丹を威圧したことで、「偽りの大漢」が復国し、漢人の天下が再び継続されたとも言える。当時の遼は、後世の西遼(耶律大石)のように高度に漢化し、炎黄を祖先と仰ぐ政権ではなかった。耶律徳光が本当に中原を支配していたら、それは清の多爾袞(ドルゴン)のような「異民族による漢地支配」が、数百年も早く実現していたかもしれない。
南唐の野心は北方にとどまらず、南方でも積極的だった。閩国が内乱に陥ると、即座に福建へ出兵し、建州・汀州(閩北・閩西)を占領。さらに湖南にも進出し、一時は馬楚(南楚)を滅ぼすまでに至った。しかし、その後、楚人の反撃により追い出され、湖南は再び独立を果たす。
だが、正直に認めざるを得ないのは、南唐には志気こそあれ、戦闘力は劣っていたということだ。南楚を一時滅ぼしたものの、結局はその地を維持できず。また、契丹と戦って中原を奪還しようとしたが、その努力は後漢・後周の「嫁衣(かいい)」となってしまった。徐州を攻めて後周に挑んだ際も、周の太祖・郭威に敗れて撤退を余儀なくされた。さらに悲劇的なのは、この北伐が逆に周の世宗の南征を招き、淮南十四州を失う結果となったことである。
だが、誰が南唐のこの「愚かなる勇気」を覚えているだろうか?
たとえ「戦下手(いくさへた)」であっても、南唐には高潔な夢があった。それは、民族の重荷を背負い、中原の漢人を救おうとする使命感だった。もし漢人がみな呉越のように、強者を見れば即座に跪く「フェラ(feeble, 怯懦な者)」ばかりだったなら、漢人の歴史はすでにそこで終わっていたかもしれない。
歴史が前進できたのは、果たして「皇越」のような臆病な者たちのおかげだろうか?
否。それは、南唐のような「愚者」が、無謀と知りつつも一歩を踏み出したからこそである。